認定看護師紹介
<日本精神科看護協会認定>
精神科認定看護師
|
|
うつ病は児童期から老年期まで幅広く見られ、誰でもかかる可能性がある病気です。 原因としては、心配や過労、ストレスが続いた時、孤独や孤立感が強くなったり将来の希望が見出せないと感じた時などがあげられます。 また、悪性疾患や身体損傷など大きな病気に合併してみられることもあります。 私は認定看護師として、効果的な入院・通院治療を支援するために、患者さんの発病過程、 年齢や家族背景・学業や就業など一人ひとりの状況をふまえ、 認知力・体力の回復に向けて心理教育をはじめとしたプログラムを行っています。 また、ご家族や職場関係者に対しても患者さんとの接し方や疾患教育を行い社会復帰に向けて支援しています。 特に職場復帰に向けては、職場・病院の関係者で会議を行い、 病状に合わせた社会復帰を患者さんと一緒に考えて行けるよう支援しています。 |
 佐藤 真紀 佐藤 真紀 |
精神科医療は病院中心から地域生活中心への移行が今まで以上に求められ、 外来看護は入院から退院後の生活まで幅広い関わりが必要となります。 入院時から退院支援マネジメントフローを活用し、病棟・多職種と連携を図り、 継続看護の強化に努めています。 退院前は病棟での多職種カンファレンスに参加し、 退院後の療養環境についての情報を共有し、生活指導に繋げています。 退院後は受診時の待ち時間を活用し、面接を行い退院後の地域生活の状況を確認し、 不安を抱えていたり、生活のしづらさを感じている患者さんには、 医師や精神保健福祉士に情報を提供し、早期に対応ができるように連携を取っています。 患者さんが自分の居場所で安心し充実した生活が送れることを目指して、 ご家族や地域の方々と連携を図っていきたいと考えています。 |
|
|
我が国の高齢化は年々進み、社会環境から受けるストレスは大きく、精神科医療の現場において身体疾患の合併率も高くなると言われています。 |
|
|
私は2022年に精神科認定看護師の資格を取得しました。山梨県立中央病院の精神科身体合併症病棟を合わせると18年ほど精神科領域に携わり看護実践をしています。患者さんは精神症状によってうまく伝えられないことがあり、私はそこに寄り添って一人ひとりの思いを大切にしながら、その人にとっての「生活のしやすさ」に焦点を当てた支援を行うことが重要だと考えています。また現在私は自殺予防に関する支援を担当しており、症状によって生じる社会的孤独感や考え方のゆがみを軽減できるように、その人らしく生活できる支援を多職種と連携し実践しています。 |
<日本看護協会認定>
認知症看護認定看護師
|
|
認知症の患者さんは中核症状や行動心理症状により、本人の感じている事と周囲との環境にずれが生じやすく、生きにくさを感じやすくなっています。また、苦痛やストレスを上手に表現できない事で、一見不可解な行動や問題行動と捉えられてしまいがちです。その行動の背景にある思いを把握できるように関わり、患者さんに適した関わり方を考えていく事が大切になります。入院生活という慣れない環境で治療を行ううえでは、薬物治療だけではなく「環境」を整えていく必要があります。私達医療従事者も患者さんにとっての環境要因であることを意識しながら関わり、安心・安全な生活が送れるように支援していきます。患者さんの思いを尊重しながら住み慣れた地域での生活が継続出来るように、ご家族や地域の支援者と共に考え、支えていきたいと考えています。 |
感染管理認定看護師
 藤森 千晶 藤森 千晶 |
感染管理認定看護師は、科学的根拠に基づき、患者さん、ご家族、そして職員を含む病院に関わる全ての方々を感染症から守る役割を担っています。 特に精神科病院では、患者さんの病状によって感染予防行動が難しい場合や、病院の構造・環境による独自の感染リスクがあります。私はこの特殊性を深く理解し、患者さんの尊厳を尊重しながら、一人ひとりの状況に合わせた感染対策の実施を目指しています。 全職員を対象とした感染対策研修会の開催や感染対策委員会メンバーと協力し、手指衛生の徹底、適切な個人防護具の使用、環境整備など実践力の向上に努めています。また、感染症発生時には迅速な拡大防止対応を行います。 これらの活動を通じて、患者さん、ご家族、職員すべてが安心して過ごせる安全な療養環境を整え、質の高い医療提供に貢献できるよう、日々尽力してまいります。 |
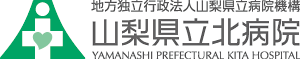
 猪又 加寿子
猪又 加寿子

 石川 大輔
石川 大輔