初期臨床研修プログラム
目的
本プログラムの目的は、卒後臨床研修を通じて多様化する医療に対応できる人材の育成を行うことです。 指導医のもとで、医師としての人格と見識を磨き、将来専門とする分野に限らず、日常診療で頻繁に遭遇する Common Disease に適切に対応できるよう、プライマリケアの基本的な診療能力(態度、技能、知識)を身につけることを目的としています。
特徴
当院は、1973年より46年の長きにわたり、臨床研修指定病院として研修教育を行ってきました。 その経験を踏まえて、本プログラムは厚生労働省の「臨床研修の到達目標」を達成できるように計画されています。 各科とも症例は豊富で、症例検討会、抄読会も活発に行われています。 他科との交流も円滑であり、多くの指導医の指導を受けながら、プライマリケアに対応できる診療能力を習得することが可能です。
指導は各科ともにマンツーマンで行われますが、指導医、後期研修医、上級臨床研修医による手厚い指導、すなわち重層屋根瓦方式が確立しています。 臨床研修終了時には各科の認定医、専門医の受験資格の一部を満たすことができます。
救急医療体制は整備されており、研修医は指導医とともに二次・三次救急に積極的に参加します。 BLS や ACLS のコースも院内で定期的に開催されており、研修期間中に国際レベルの資格を得ることが可能です。
初期研修医基本理念
1 研修医基本理念
すべての研修医が確かな知識と医療技術を礎に成長を続け、患者に信頼され安心を与え、自信をもって医療を行うことができる医師に育つ。
2 研修目標と基本方針
“5つの基本方針が私たちの初期臨床研修を支える”
1) 基本的な手技・知識・問題解決能力を身に着ける
① 2次救急、病棟、外来での基本医療を習得する。
② 症例提示(presentation)能力を習得する。
2) Professionalな医師を目指す
① 患者の目線に立つ。患者の尊厳を大切にする。
② 疾患ではなく患者を治療する。
3) コミュニケーション能力を身に着ける
① 患者・患者家族とのコミュニケーション能力を身に着ける。
② 多職種とのコラボレーション能力を身に着ける。
4) 山梨の医療を考える
① 中核病院が地域医療機関と連携する形を学ぶ。
② 医療の社会的役割を理解する。
5) 学術的探求と臨床研究能力を習得する
① 症例報告と学会発表を習得する。
② 臨床研究を経験する。
理事長からのメッセージ

山梨県立病院機構理事長
東京大学名誉教授
小俣 政男
重層屋根瓦方式 “Touch First but Protected”
Touch First
どのように患者さんが来るかわからない状況に投げ込まれ、医師として動じず冷静に診療するというトレーニングをまず行う必要がある。 ある年の8月の救急には、子どもの発熱、盲腸炎、過換気症候群、自殺企図、急性腹症、気管支炎、高血圧症、インフルエンザ、胃潰瘍、心筋梗塞、虫刺され、 腸閉塞、めまい、前立腺肥大など多岐に渡る患者さんが来る、まさに暑い夏です。この多様性を1年間経験し自ら対応できるように努める、と同時に、来るべき 1年生の “Senior” としての役割を果たす。 それこそ屋根瓦方式です。
Protected
しかし、ただそのExposureに諸君を投げ出すわけではありません。そこで機能するのが、 “重層屋根瓦方式”です。臨床に身をおいて10~30年のベテラン、さらには救命救急センターの心肺停止から蘇生を行うチームまで、幾層にも多くの専門医 が後ろに控えています。初動の対応を、研修医が安全に行えるシステムがすでに当院にはあります。現在は、臨床研修 (1年、2年) 51名が研修に励んでいます。
後期研修に向け
自身、27歳 (45年前) で米国Matching Programに応募、渡米し6年間の米国体験を有する。その実体験から、これからの、卒後研修の真価が問われるのは実は「後期研修」ではないかと考えます。
若き医師の多様な願望に答える為、「後期研修」期間には特に、研修の幅に “Spectrum” を持たせる必要があります。 “First Touch”から、専門医の取得、更に当院で蓄積された臨床データのPublication或いは海外留学など、専門性のある後期トレーニングの質改善に 努め、毎年30名程度 (卒後3 – 5年) が研修に励んでいます。
人生は一度、しかも最初の五年
医師になってからの最初の数年間がその後の成長にいかに大切な時期であるかを、50年間臨床に携わった今でも実感しています。
意欲あふれる皆さんが当院の研修に参加されたあかつきには、全職員一致団結して将来の日本の医療を担う人材の育成に努めることをお約束いたします。
院長からのメッセージ
院長
小嶋 裕一郎
当院は高度救命救急センター・総合周産期センターを備え、また,全国で32施設のみが選ばれたがんゲノム医療拠点病院の一つとなっています。また、ドクターヘリを有する県内唯一の三次救急病院でもあります。医師数は現在228名で、うち専攻医49名・研修医51名と皆様の仲間となる若手医師が多く在籍しています。毎月
院内全体のスタッフを対象に開催する抄読会であるMSGR( M e d i c a lSurgical Ground Rounds)、年に1回1年目研修医を対象とした症例報告および、2年目研修医を対象のテーマを決めた臨床研究発表会をはじめ、多くの研修会を開催しています。さらに、希望がある専攻医は週に1回ゲノム解析センターで遺伝子解析を行う研究が可能です。
一方、アメニティの充実も図り、研修医の住居である防音が完璧に施されたレジデントクォーターを完備し、また海外留学制度も充実しています。
医学生、初期研修医の皆さん、当院での初期研修・後期研修を開始し、ぜひ我々の仲間に加わりませんか。
臨床研修プログラム責任者のコメント

教育研修センター統括部長
飯室 勇二
当院の特徴は、地域中核病院としての救急医療と各分野での最先端医療の提供、及びそれらを支える教育及び学術活動、の両立にあります。
【救急医療】
ドクターヘリとドクターカーを駆使し、山梨県全域をカバーする医療圏の3次救急と週2回の2次救急当番を行っています。1年 次・2年次・中堅医師・上級医が重層屋根瓦方式で初期対応を行っており、当院プログラムに参加していただければ基本的医療技術を安全・確実に習得できま す。
【教育・学術活動】
医師になってからの数年間が、その後の医師としての成長にいかに大切な時期であるかは、誰もが認めるところです。上級 医、中堅医師からの指導はもちろんですが、若き先輩医師たちによるマンツーマン指導により、きめ細かい教育を行っています。また、皆さんの今後の活躍の裏 づけとなる学術活動にも、臨床研修の時期から積極的に参加していただきます。
まずは、当院へ一度見学に来てください。若き医師たちが生き生きと躍動している姿を目の当たりにすることが出来ます。首都圏に隣接しつつ、自然あふれる山梨の地で、よき仲間と自分を高めていく、そんな研修に参加してみませんか。
研修医のコメント
伊藤 まい(令和6年度 二年次研修医)◆総合研修プログラム
山梨県立中央病院での初期臨床研修の魅力は、二次救急とアットホームな雰囲気にあると思います。当院は県内の救急医療の中核を担っており、二次救急においても当院が引き受ける患者数は県内で最多となっています。二次救急では研修医が主体となって診察から初期治療や他科へのコンサルトまで行います。初めは右も左も分からない状態で戸惑いや焦りもありましたが、多くの症例を経験していくうちに、知識・経験・度胸が付くようになります。
また、二次救急の場には必ず上級医がいて、相談やフィードバックを行うため、積極的に学んでいく姿勢が自然と身につきます。上級医の先生方は熱心で気さくな方ばかりで、研修医同士も非常に仲が良いので、日々楽しく医療を学ぶ事ができます。
私は出身も大学も県外ですが、疎外感は全く感じず、充実した研修生活を送っています。当院で皆さんと共に働ける日を心待ちにしています。
長井 陽汰(令和6年度 二年次研修医)◆小児科重点プログラム
私が当院を志望した理由は救急対応力を身に着けつつ、将来の志望分野に沿った研修を行うことが出来るからです。当院の2次救急では研修医自ら診察、治療方針の検討、上級医へのコンサルトまで行います。判断に迷うような場面では上級医の先生に相談しながら診療を行います。フィードバックもあり実践的な力を養うことができます。また、私は小児科重点プログラムで研修を行っていますが、小児科の研修では救急外来での初期対応を中心に幅広い症例を経験できます。新生児内科での研修を選択することも可能で、超出生体重児を含む新生児の集中治療に携わることができます。研修医のうちから専門的な診療を経験でき、実際に研修して多くの学びを得られました。
当院では1人1人の将来に必ず役に立つ研修を行うことができます。語り切れない多くの魅力があるので興味のある方はぜひ見学にいらしてください。
皆さんと一緒に働ける日を心待ちにしています。
臨床研修プログラムの紹介
総合研修プログラム
【プログラムの基本的な考え方】
-
自由度が非常に高く、様々なニーズに対応できます。
- 2年時の8週目までに必修科目を研修して基礎を固め、2年次の9週目からは自由度の高い研修プログラムを自分で組み立てることが出来ます。
【必修科目について】
-
内科研修では、内科詳細科(群)の5つ(「循環器・糖尿病内分泌」、「呼吸器」、「消化器」、「腎臓・リウマチ・膠原病」、「総合診療・感染症」)のうちから3つを選択し、それぞれを8週研修します。※一部の詳細科(群)に希望が集中した場合は、調整となります。
- 救急科研修では、高度救命救急センターにて三次救急を8週間研修します。勤務はシフト制ですので、無理なく研修することが可能です。
-
2020年度からの臨床研修制度見直しに伴い、「外科」、「小児科」、「産婦人科」、「精神科」を4週間ずつ研修します。「精神科」のみ精神科専門病院である県立北病院での研修となります。
- 麻酔科研修は、4週間の必須とします。救急科と連続して研修することにより、気管挿管等の知識・技術をマスターできます。
- 地域医療研修は4週間の必修とし、9の地域医療拠点病院から選択します。
※2年次の9週目以降の研修となります。 - 新たに必修となる一般外来研修は、2年次に行います。院内では一般外来の指導医の下で継続的な診察を経験し、院外では主に地域医療研修施設にて外来研修します。トライアル中ですので変更の可能性有。
[地域医療研修病院]
上野原市立病院、大月市立中央病院、峡南医療センター市川三郷病院、 峡南医療センター富士川病院、組合立飯富病院、都留市立病院、北杜市立甲陽病院、北杜市立塩川病院、山梨市立牧丘病院、山梨赤十字病院、道志村国民健康保険診療所
【選択診療科について】
-
104週(2年間)のうち、48週間を自由に選択できます。
(但し、4週ごとの研修を原則とします。) - 神経内科、保健・医療行政、リハビリテーション、予防医学、精神科は他施設で研修します。
- 選択科としての内科研修は、上記5つの詳細科群での研修(病棟ごとの研修)、各詳細科ごとの研修のどちらでも選べます。
産婦人科小児科重点プログラム
【プログラムの基本的な考え方】
- 産婦人科診療全般 、 小児科 、小児外科 および新生児 内 科( NICUの基礎を修得し、さらに、当院 の特徴である、高度周産期医療、婦人科がん治療を多数経験すること 、 小児新生児での 専門分 野での研修を深めること で、 将来その分野のスペシャリストになるための基礎を学べます。
- 産婦人科・小児科・小児外科・新生児内科を優先的に研修できます。
- 山梨大学医学部附属病院 小児科で研修が可能です。
【必修科目について】
- 総合研修プログラムの必修科目に加え、小児科及び産婦人科を全体で16週研修します。
- 小児科研修は山梨大学小児科での研修も可能です。
【選択診療科について】
- 104週(2年間)のうち、48週間を自由に選択できます。
(但し、4週ごとの研修を原則とします。) -
神経内科、保健・医療行政、リハビリテーション、予防医学、精神科は他施設で研修します。
-
選択科としての内科研修は、上記5つの詳細科群での研修(病棟ごとの研修)、各詳細科ごとの研修のどちらでも選べます。
臨床研修のためのミーティング
臨床研修においては、個々の研修医が個々の入院症例の担当医として診療することにウエイトが置かれますが、研修医が定期的に集合してミーティングを持つことも大切な要素です。
当院では、各診療科カンファレンスや臨床病理検討会(CPC)のほか、MSGR(Medical Surgical Ground Rounds)という独創的な学術集会や各種キャンサーボードが開かれ、様々な学びの場が用意されています。また研修医が主役の発表会「研修医発表会」も毎年開催しています。
過去3年間の研修医出身大学
・山梨大学・自治医科大学・信州大学・東海大学・福井大学・東京医科大学・東京医科歯科大学・北里大学・富山大学・東北大学・東邦大学・東京慈恵会医科大学・産業医科大学・金沢医科大学・秋田大学
当院の新専門医制度
国等認定・指定施設

- 保険医療機関
- 地域医療支援病院
- 高度救命救急センター救急告示病院
- 基幹災害拠点病院
- 第1種感染症指定医療機関
- 総合周産期母子医療センター
- 臨床研修指定病院
- 歯科医師診療研修指定病院
- 外国医師・外国歯科医師臨床研修指定病院
- がんゲノム医療拠点病院
- エイズ治療中核拠点病院
- 臓器提供施設
- 指定自立支援医療機関(育成医療・更正医療)
- 難病医療協力病院
- がん診療連携拠点病院
- 難病医療費助成指定医療機関
- 小児慢性特定疾病医療費助成指定医療機関
学会認定・指定施設


- 日本内科学会内科専門医教育施設
- 日本呼吸器学会認定施設
- 日本消化器病学会指導施設
- 日本消化器内視鏡学会指導施設
- 日本循環器学会専門医研修施設
- 日本内分泌学会認定教育施設
- 日本糖尿病学会認定教育施設Ⅰ
- 日本腎臓学会研修指定施設
- 日本透析医学会研修認定施設
- 日本血液学会研修施設
- 日本リウマチ学会研修施設
- 日本臨床腫瘍学会認定研修施設
- 日本がん治療認定医機構認定研修施設
- 日本小児科学会専門医研修施設
- 日本小児循環器学会専門医修練施設
- 日本外科学会専門医制度修練施設
- 日本消化器外科学会専門医修練施設
- 日本乳癌学会認定施設
- 日本小児外科学会認定施設
- 日本整形外科学会認定研修施設
- 日本形成外科学会教育関連施設
- 日本胸部外科学会認定医指定施設
- 日本脳神経外科学会認定医訓練施設-A項
- 日本皮膚科学会認定専門医研修施設
- 日本泌尿器科学会専門医研修施設
- 日本周産期・新生児医学会認定基幹施設
- 日本産婦人科学会専門医制度卒後研修指導施設
- 日本眼科学会専門医制度認定研修施設
- 日本耳鼻咽喉科学会専門医認定研修施設
- 日本麻酔学会麻酔指導病院
- 日本緩和医療学会認定研修施設
- 日本核医学会教育認定施設
- 日本医学放射線学会放射線科専門医修練施設
- 日本救急医学会指導医指定施設
- 日本病理学会認定病院
- 日本臨床病床理学会認定研修施設
- 日本成人先天性心疾患学会連携修練施設 等
掲載内容に関するお問い合わせ
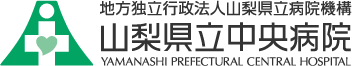
教育研修センター
- 電話番号
- 055-253-7111(代)

