倫理指針
山梨県立中央病院の倫理指針
Ⅰ 職業倫理指針
- 私たちは、自らの責任と義務を自覚し、教養を身につけ、品格を高める努力を怠りません。
- 私たちは、人命を最大限に尊重し、人道的立場にのっとり、医療を実践します。
- 私たちは、患者さんに係る個人情報を守秘します。
- 私たちは、国籍・人種・宗教・信条等に左右されることなく、公平・公正な医療を提供します。
- 私たちは、知識・技術の習得に努め、医療水準を高め、最善で最良の医療の提供を目指します。
- 私たちは、良好なコミュニケーションを通じて、患者さん・ご家族との信頼関係を築きます。
- 私たちは、各職種の専門性を尊重し、チーム医療の実践に努めます。
- 私たちは、医療に伴う様々なリスクを十分に意識し、医療安全に心がけます。
- 私たちは、当院が地域から求められる役割を熟知し、地域社会に貢献します。
Ⅱ 臨床倫理指針
- 私たちは、患者さんの尊厳・自己決定権を尊重し、十分な「説明と同意」(インフォームド・コンセント)を繰り返しながら医療を進めます。
- 私たちは、患者さん・ご家族に、第三者から当院の治療方針の評価を受けるセカンドオピニオンをお勧めします。
- 私たちは、学会や院内で制定された各種ガイドラインにのっとり、標準的医療を包含した医療を実践します。
- 私たちは、身体抑制を行わない医療・看護を目指します。
- 私たちは、現在生じている個々の倫理的課題について、多職種カンファレンスで討議を重ねることにより解決を図ります。
- 私たちは、倫理的な課題が重大あるいは解決困難と考えられる場合は、当院の倫理委員会に判断を委ねます。
- 私たちは、新しい医療行為を導入する場合には、当院倫理委員会に審議を要請し、その承認を得ることを前提とします。
- 私たちは、医療に係る普遍的な倫理的課題を拾い上げ、当院倫理委員会にてガイドラインを整備します。
- 私たちは、臨床研究を実施するにあたっては、当院に設置された臨床研究・ゲノム研究倫理審査委員会に倫理審査を要請し、その承認を得ることを前提とします。
- 私たちは、治験を実施するにあたっては、当院に設置された治験審査委員会に倫理審査を要請し、その承認を得ることを前提とします。
医療行為に関する倫理指針
集中治療領域における終末期の医療行為
回復の見込みがなく数日以内に死亡すると推定される人工呼吸器を装着した重症脳障害の患者さんであって、人工呼吸治療を中止すると24時間以内に死亡すると推定される場合に、患者さんのご家族が人工呼吸器の離脱を強く希望する場合の対応
集中治療領域における終末期の医療行為においてもその大多数は治療行為を継続することが基本である。しかし、時には延命治療の中止を選択せざるを得ない場合や、状況から中止が望ましい場合と思われる場合もある。その場合、中止するかどうかの検討は、「救急・集中治療領域における終末期医療に関するガイドライン~3学会からの提言~」(平成26年11月4日 作成)(日本集中治療医学会、日本救急医学会、日本循環器学会)に準拠し、複数の医療従事者による複数回の検討の結果によるべきである。
さらにチームが判断に迷う場合は倫理委員会に事例の提示を行い、倫理委員会にて検討する。
1.生命機能回復不能の判定・確認
生命維持機能が絶対的に不全で回復が望めず、数日以内に死亡すると推定される場合に、人工呼吸器の中止を考慮する。
患者さんのご家族が予定の立つ状態で揃って看取ることを希望している状況と考えられることから、人工呼吸器を中止すると24時間以内に死亡すると推定される場合が検討の対象となる。
2.患者さん・ご家族の意向・意思の確認
患者さんが生前に延命治療を拒否する意思を明確にしている場合は、これを一義的に尊重し、これに従う。明確な意思表示は、事前指示(advance directive)や生前発行遺言(living will)にて示される。
患者さんによる書面での意思表示がなくても、患者さんがご家族に口頭で延命処置拒否の意思を伝えていたことが事実として確認されれば、治療方針を決めるうえでの重要な参考となる。
診療中などに患者さんの言葉で意思表示があった場合にその旨を主治医がカルテ記載したものは、後の患者さんの意思の推定の際の参考となる。この場合、ご家族の立会や確認の事実が付記されていれば、患者さんの意思表示としての重みは増す。
患者さん自身の延命治療拒否の意思表示が確認できている場合は、ご家族内に反対や異論が出た場合でも、患者さんの意思に従い、主治医は粘り強くご家族に説明・説得・相談を繰り返す。
患者さんの意思確認が不可能な場合は、ご家族に意見を求める。この場合の家族とは、親族のみならず、最も親しい友人なども含まれる。あらかじめご家族内でキーパーソンを決めてもらい、伝達を一本化し、ご家族で話し合った結論を、キーパーソンを通して主治医に伝えてもらう。
3.医療チームによる繰り返しの検討
チーム医療が基本の現在の医療では、「中止・離脱」に対する医療者の意見・決定も主治医単独や当該科の医師のみでは許されない。少なくとも、主治医を含めた当該科の医師団、当該病棟の看護師、当該病棟の薬剤師、必要に応じて他診療科の医師を集めたカンファレンスを、繰り返し(少なくとも2~3回)行うことが必要である。その結論の如何に拘わらず、そのプロセスは毎回詳細にカルテに記載して残す。なお、上記の医療チームの構成員の一部は、状況に応じて省略できる場合がある。
4.倫理委員会への諮問
医療チームによる繰り返しの検討を経ても、家族内の意思統一が得られない場合には、医療チームによる検討プロセスを別紙の様式に則り記載し、委員会へ提出し、その助言・承認を得る。
説明と同意
当院では、全ての医療行為において、患者さんへの説明と同意を得ることとしています。
その方法には、個別に書面で行うものと、口頭で行うものがありますが、どちらの方法で行うかは個別に各部門で定めています。
ただし、一般に個別の同意を必要としない医療行為については、あらかじめ診療科共通のものとして以下の通りお示しし、包括的な同意をいただいたものについては、口頭での説明、同意確認で対応させていただいております。疑問がある場合には、医師、看護師までお申し出ください。
【一般項目】
問診、視診、理学的診察、聴診、体温測定、身長測定、体重測定、血圧測定、栄養状態の評価、栄養指導、食事の決定など
【投薬・投与】
通常の投薬、注射、点滴ラインの確保、持続皮下留置針挿入、酸素投与など
【検査・モニター】
血液検査、尿検査、畜尿、痰などの微生物学的検査、検体の病理・細胞診検査、心電図・脈波、肺機能・エコー・脳波・超音波検査・呼吸検査・呼気ガス分析・筋電図・サーモなどの生理検査、X線一般撮影、X線透視撮影、造影剤を用いないCT・MRI、RI(アイソトープ)検査、心理検査、心電図・経皮酸素飽和度測定・動脈圧・呼吸喚起・BISモニター・筋弛緩モニターなどのモニター、パッチテスト、皮内テスト、スクラッチテスト、ツベルクリン反応、最小紅斑量測定などの皮内反応検査、アレルギー皮膚テスト、手術・透析・血管造影等を行う場合の、梅毒、B型肝炎、C型肝炎、エイズ(HIV抗体)の感染の有無を判定する血液検査
患者さんの安全確保のために、治療上必要な場合、カメラによる患者さんの様子のモニター
【処置】
痰などの吸引、鼻管カテーテル、膀胱留置カテーテル、う歯(虫歯)、歯周病、義歯の検査と治療、口腔ケア
上記の診療行為は一定以上の経験を有する者によって行われます。
採血や注射等は、病気の診断や治療を行うために必要ですが、血管や神経の走行、血管のもろさ、血液の固まりにくさ、痛みの感じ方など、患者さん個々の異なる要因で、医療者が適切(標準的)な手技で行っていたとしても、「神経損傷」「止血困難」「皮下血腫」「血管迷走神経反応」などの合併症・偶発症が起こることがあります。
【チームの活動】
診療科のほかに、患者さんのケアを充実させるために、必要に応じて、感染対策チーム、栄養サポートチーム、緩和ケアチーム、褥瘡ケアチーム、精神科リエゾンチームなどが診療に参加することがあります。
【研修医、医療系学生の診療への参加、見学】
上記の診療行為は指導医等の管理のもと研修医等が施行することがあります。また、特に軽微で危険性の少ないと考えられる医療行為は医師・医療者の指導監督のもと、医学生・看護学生が関わることがあります。
【調剤薬局等への情報提供】
薬物療法の安全性向上を目的とした円滑な連携のために、必要に応じて調剤薬局や他の医療機関に対して患者さんの薬歴、副作用歴、臨床検査値、お薬に関する説明内容等の情報を提供させて頂きます。
【防犯、監視カメラの運用】
患者さんの安全確保のために、患者さんの様子を含め院内をカメラでモニターさせていただいております。
【プライバシーの保護】
院内では、カメラ、スマートフォン、ビデオ等による撮影は、他の方のプライバシーを侵害する恐れがありますので、禁止させていただきます。
宗教上の理由で輸血を拒否される場合
宗教上の理由で輸血を拒否される場合については、生命を守るという医療人としての基本的な立場を重視する。従って、輸血の可能性が否定できない場合は無輸血手術ないし無輸血治療を前提とした治療を行うことは出来ず、原則として患者さんの受け入れを行わないことが病院の方針である。
イ 輸血まで時間がある場合
予定手術など輸血まで時間がある場合は、当院では無輸血を全うして治療することができないことを話してご理解を得た後、適切な医療機関を紹介するか、または患者さんに医療機関を探していただき、当院として患者さんの受け入れは行わない。
ロ 緊急に輸血が必要な場合
患者さんが救急で来院し、転院を待たずすぐに輸血が必要な場合は、輸血が必要なことをご本人やご家族に話し理解を求める。仮に理解が得られない状態であっても、患者さんの生命維持に輸血が必要と主治医が判断した場合は、ご本人とご家族に輸血をすることを告げ、必要な輸血を行う。輸血が必要かどうかの判断は主治医に委ねる。この判断および医療行為の責任は、全て病院に帰属する。なお、主治医は上記を判断する場合、上席医師と協議しその内容を記録する。
未承認新規医薬品等を提供する場合
当院では未承認新規医薬品等(医薬品又は高度管理医療機器であって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に規定する承認又は認証を受けていないもの)の提供に関し、各診療科等から提出される申請書を確認の上、未承認新規医薬品等適否決定部会にて十分に審議を行った上、使用の適否について決定しています。
承認されたものについては下記の通りです。
○注射用塩化カリウム製剤(KCL注20mEqキット「テルモ」/20mL)の適応外使用(2024年10月)
掲載内容に関するお問い合わせ
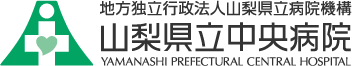
山梨県立中央病院
- 電話番号
- 055-253-7111(代)
