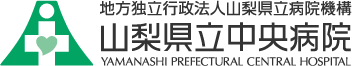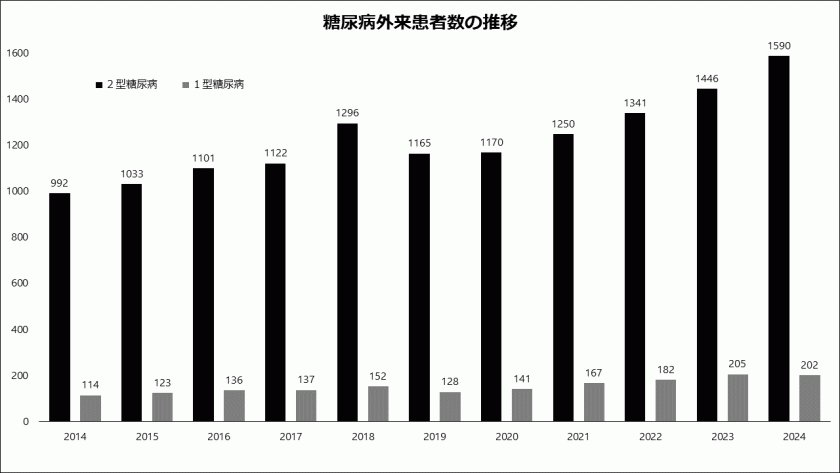内科(糖尿病内分泌)
糖尿病、内分泌疾患(甲状腺疾患、副甲状腺疾患、視床下部・下垂体疾患、副腎疾患)、二次性高血圧を中心に診療を行っています。
スタッフ紹介
| 医師 | 専門分野/出身大学 | 資格・所属学会等 |
|---|---|---|
|
副院長 |
糖尿病、内分泌代謝 | 日本内科学会総合内科専門医・指導医 日本糖尿病学会専門医・指導医 日本内分泌学会評議員 医学博士 |
| 信州大学 (昭和61年卒) |
||
|
臨床試験管理センター統括副部長 |
糖尿病、内分泌代謝 | 日本内科学会総合内科専門医・指導医 日本糖尿病学会専門医・指導医 日本内分泌学会専門医・指導医 医学博士 |
| 山梨大学 (平成14年卒) |
||
| 部長 祢 津 昌 広 ねづ まさひろ |
糖尿病、内分泌代謝 | 日本内科学会総合内科専門医・指導医 日本内分泌学会専門医・指導医・評議員 医学博士 |
| 東北大学 (平成21年卒) |
||
| 専攻医 石井 玲央 いしい れお |
山梨大学 (令和3年卒) |
|
|
専攻医 |
東海大学 (令和4年卒) |
|
|
専攻医 |
山梨大学 (令和4年卒) |
【日本糖尿病学会認定教育施設】
【日本内分泌学会認定教育施設】
<糖尿病>
外来診療
2024年の外来患者数は、定期フォロー中の患者さんだけで約1,800人になります。最近は妊娠糖尿病の増加に伴い、新規インスリン導入も多く、外来での導入も可能です。教育に関しては、専門看護師および栄養相談科の管理栄養士による個別指導を行っています。専門看護師によるフットケア外来に加え、2021年からは糖尿病透析予防指導も本格的に開始しています。
11月の糖尿病週間には当院糖尿病療養指導士会を中心にイベントの開催を行い、糖尿病の啓蒙活動も行っています。
糖尿病の合併症の診断と治療は、眼科、腎臓内科、循環器内科、泌尿器科などとの緊密な連携のもと行っています。

「糖尿病患者さんのつどい」の様子
入院診療
現在、糖尿病診療においても、入院診療に力を入れています。糖尿病教育入院はクリニカルパスを使用し主に1週間入院のコースで行っています。
最近は糖尿病患者の高齢化に伴い、感染症などの合併症治療や、血糖高値で手術ができない場合にインスリンで術前コントロールを行う患者さんも増えているのが現状です。
これらの入院には糖尿病専門医だけではなく、病棟看護師をはじめ栄養相談科の管理栄養士・検査部の検査技師・薬剤部の薬剤師・リハビリテーション科の理学療法士と約40名のスタッフ(そのうち7名が日本糖尿病療養指導士の資格を有する)が教育、治療に参加しています。
また、インスリン注射を行っている患者さんには血糖自己測定器を貸与し、血糖を測定し糖尿病コントロールに役立てていただいています。連続的に血糖値をモニタリングできるFGM(フラッシュグルコースモニタリング)を使用する患者さんも増えてきています。1型糖尿病患者のインスリンポンプ療法(CSII)も、積極的な導入を行っており(現在16名に使用)、2024年からは基礎インスリン・補正インスリンの自動調整・投与機能を有する780Gシステムが使用可能となり、当科も適宜導入・切替えの対応をしています。
毎週木曜日には糖尿病専門チームによる各病棟回診も実施しています。
糖尿病患者数は非常に増加しており、当院だけでの対応は困難ですが、病診連携を活用し円滑な診療を目指しています。
<内分泌、二次性高血圧>
各種の負荷試験や画像検査などによる正確な診断と治療に力を注いでいます。
甲状腺疾患は症例数が多く、現在腫瘤性病変の精査・加療は耳鼻科に依頼し、当科は甲状腺ホルモンの異常(バセドウ病・慢性甲状腺炎など)について診断、治療を行っています。
二次性高血圧(内分泌性高血圧)、下垂体疾患、副腎腫瘍の内分泌学的精査目的の紹介も近年増加傾向です。外来での負荷試験を行い、より多くの方の迅速な診断・治療を目指しています。
特に、原発性アルドステロン症における選択的副腎静脈サンプリングも循環器内科に協力していただき、最終的な治療方針は当科でお伝えしています。
また、クッシング症候群や褐色細胞腫の患者さんについては、1-2週間入院していただき、診断と術前内科管理を兼ねた治療を行うほか、外来では鑑別困難な副腎腫瘍や下垂体腫瘍、副甲状腺疾患の患者さんにも、数日間の検査入院を行っています。
診療実績
2024年
| 病名 | 外来患者数 | 入院患者数 |
| 1型糖尿病 | 202 | 20 |
| 2型糖尿病 | 1590 | 113 |
| バセドウ病 | 323 | ー |
| 橋本病 | 92 | ー |
| 下垂体機能低下症 | 42 | ー |
| 副甲状腺機能亢進症 | 60 | ー |
| 副甲状腺機能低下症 | 14 | ー |
| 原発性アルドステロン症 | 48 | ー |
| 褐色細胞腫 | 22 | ー |
| クッシング症候群 | 13 | ー |
★ 医学生(4~6年次)、初期研修医の当科見学を随時受付しております。
希望する場合は、下記連絡先のメールアドレス宛にお申込みください。
山梨県立中央病院 総務課 庶務担当
E-mail: chubyo@ych.pref.yamanashi.jp