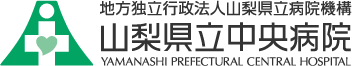中央手術室
人工心肺業務
心臓手術や大血管手術の時には心臓を止めて手術を行います。そのため、循環・呼吸の代行をする人工心肺という装置が必要になってきます。 臨床工学技士は安全に手術を行うために、心臓外科医、麻酔医、看護師と連携し、人工心肺操作を行っています。 人工心肺の構成としては、血液ポンプ(心臓の代行)、人工肺(肺の代行)、貯血器、回路、心筋保護回路、脳循環回路などで成り立っています。
その他、腹部大動脈瘤手術時などでの自己血回収を行っております。 これはなるべく輸血を回避するために手術中の出血を回収し、洗浄赤血球を作る装置のことでこの操作を行います。
また、泌尿器科、外科、婦人科ではロボット支援下手術(ダヴィンチ)を行っており、臨床工学士はロボットシステムの管理、設定にダヴィンチチームの一員として携わっています。
 人工心肺装置 |
 心筋保護装置 |
 PCPS装置 |
| <使用器機> | 人工心肺装置 | 1台 |
| 心筋保護装置 | 3台 | |
| PCPS装置 | 3台 | |
| 自己血回収装置 | 1台 |